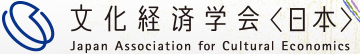私の文化経済学履歴書 川崎賢一
駒澤大学GMS学部 川崎 賢一
そもそも文化経済学会<日本>が立ち上げられた1992年頃に関係者に声をかけられて学会員となった。当時は、隣接の社会心理学を除いて、社会学者は皆無であった。私自身は、元々の専門が文化社会学で、具体的に、1970年代後半から、<ニューミュージック>と呼ばれた都市的なライフスタイルに基づくポピュラーミュージック(フォークソング、松任谷由実、サザンオールスターズ等)の実証的研究から始めて、青少年文化の研究をすすめていた。信じられないだろうが、当時文化社会学は未確立な領域で、1990年代に入ってようやく、正式な授業科目になった位で、文化研究を広い文脈から研究したかったので、文化経済学会立ち上げに参加した次第である。
学会設立当時は、文化政策や文化産業などの本格的黎明期で、一方における、文化制度の構築が叫ばれつつ、もう一方で、どのように産業化し、政治制度から独立し、自由を確立していくのかが問われていたように思う。前者は、文化庁や各自治体等の文化制度の整備、後者は、メセナ活動やNPO活動等が勃興しつつあった。私自身は、その当時、米国の社会科学研究財団(SSRC)と日本の国際文化会館(I-House)とが始めた、グローバル化に関する国際比較研究(都市・経済・政治・文化の4領域)にかかわり始め、代表的グローバルシティのニューヨーク・ロンドン・パリ・東京の内、東京の文化を担当した。その後、1994年から95年にかけて、イギリスのブリストル大学に研究滞在することになった。そして、戻ってからは、文化経済学会において、1998年から2年間、微力ながら理事長を務め、その後2022年まで、理事として、様々な活動を支えてきた。
その国際研究を経て、1996年から3年にわたり、科研費を使い、米国・英国・シンガポール・日本の文化政策の国際共同研究をマネージすることになった。ニューヨーク・バーミンガム・シンガポール・東京の4か所で、文化政策に関するワークショップを開催し、日本では、国際文化会館で2度ほどシンポジュームを開催し、その成果として、文化経済学会の学会誌に「文化政策としての<Compartmentalization Strategy>:政策・市場、家元的集団主義・同志的集団主義」(第1巻第2号、1998、17-23頁)を掲載していただいた。
その後、米英の文化政策や文化経済の動向を踏まえて、シンガポールの文化政策や文化制度について、研究を深めていった。そのため、2000年から2001年にかけて、シンガポールの南洋工科大学(NTU)で、そして、2011年から2012年にかけて、シンガポール国立大学(NUS)で滞在し、その後も、シンガポールについて、多くの研究成果を出し続けている。また、比較の幅を広げるために、2011年には、中国の上海社会科学院で、中国の文化制度の研究も行った。その結果として、欧米の文化制度研究は、第一義的に重要であることを前提として、欧米以外、特に、中国・韓国・東南アジアなどの文化制度についても、比較を通じて研究する必要を痛感し、今日に至っている。
特に、シンガポールについては、コロナ禍明けの2023年に、3年ぶりに訪問して強く感じたのは、文化制度のデジタルトランスフォーメイション(DX)化ということであった。シンガポールでは、文化政策が、政策対象として常に最後になる傾向があるが、今回もその例に漏れない。よい悪は別にして、文化のDX化は避けて通れない関門だと思う。シンガポールの例は、欧米以外にも参考にすべきモデルの一つといえるだろう。
長年にわたる学会員として、3つの提言をして、本稿を閉じたい。第一に、新しい文化階層の検討である。私は社会学出身なので、文化階層に関心を抱いてきた。この分野では、P.ブルデューを筆頭に、長年にわたる研究蓄積がある。近代化した文化システムが様々な点で変容し、文化階層も変化しつつあり、文化経済的・文化政策的側面からも明らかにする必要がある。
第二に、創造都市研究の新しい意義である。1990年代以降創造都市に関する研究が蓄積されてきた。日本では、地域文化の新しく・革新的な発展と結び付いて、頂点には、ユネスコの創造都市ネットワークを筆頭にし、日本では文化庁等が音頭を取り、創造都市ネットワーク日本(CCNJ)等が媒介的な役割を果たしてきた。文化資源・遺産を活用し、地方経済を活性化する点で、一定の役割を果たしている。その一方で、例えば、①多くの創造都市が、テーマパーク化して、集客力等の格差問題やオーバーツーリズムの問題が生じているし、②いわゆる<ふるさと納税>とリンクして、元々の創造性の主旨が歪められている。③ほとんどの創造都市で、表面的なDXに留まっている。
第三に、研究者の文化研究への姿勢をあげたい。私自身、世田谷区の芸術文化政策の計画作成、長期間にわたり携わってきて、地域との関わりがいかに大切かを身をもって認識している。しかし、長年の研究生活で得た知見では、①グローバルな文脈からスタートすることと、②欧米の経験を踏まえる一方で、それ以外の文化の研究に取り組む、ことが極めて大切だと思う。
とはいえ、文化経済学会<日本>は、私が理事を退く数年前から、組織的なイノベーションを遂げつつあり、他分野との相互乗り入れも活発になったので、更なる展開を期待したい。