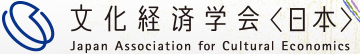九州部会活動報告(2024/3/3開催)
九州部会では、2024年3月3日に日本アートマネジメント学会九州部会との連携による研究発表会を長崎県佐世保市(会場:アルカスSASEBO)にて開催した。参加者は13名であった。当日のプログラムは次のとおりである(敬称略)。なお、両部会の連携による研究発表会は、今回で8回目の開催となる。
開会の挨拶:西島博樹(中村学園大学)
座長:岩本 洋一(久留米大学)
-
志村 聖子(相愛大学音楽学部准教授)
「伝統芸能の企画創造とキュレーションの可能性を探る–大学におけるアートマネジメント教育実践からの示唆–」
-
山口 祥平(大分県立芸術文化短期大学准教授)
「都市再生事業としての国際美術展・ドクメンタ」
-
藤原 惠洋(九州大学名誉教授)
「2022(令和4)年11月謝罪、国選定重要文化的景観「小鹿田焼の里」の誤指導究明と関係再生へ〜文化的景観の持続可能な保護と活用に関する再定義の検討・続」
閉会の挨拶:志村 聖子(相愛大学)
①報告者の志村聖子氏は、伝統芸能の次世代の担い手や享受層の拡大という課題に対し、大学におけるアートマネジメント教育の観点から、学生が伝統芸能の制作過程に参画し能動的に学べる環境づくりが必要であると指摘した。そのための試みとして、2023年に自ら大学教員として関わった伝統芸能の舞台制作ワークショップ「ファン・ゴッホの夢」の事例を紹介した。発表では、この取り組みの成果と課題について考察が行われ、学生が専門家とともに制作活動に参加することで得られた気づきや、教育環境のあり方への示唆が提示された。
②報告者の山口祥平氏は、1955年に創設されたドイツ・カッセル市の国際美術展ドクメンタの発展過程と展示空間の考察を通して、「復興遅滞地域」であったカッセル市で、このような先鋭的な文化事業を継続開催できたのは、本展に当初から都市再生事業としての役割があったからであり、また近年においてもその性質・役割が継承されていることを指摘した。地方都市における国際美術展の戦略的展開のあり方について示唆を与える内容であった。
③報告者の藤原惠洋氏は、国の重要文化的景観に選定されている大分県日田市の「小鹿田焼の里」の建物改築について、市教委文化財保護担当者が窯元に対し、仕事場の拡張は柱位置の履歴に基くべきで自由に改築できない、等と景観形成基準や文化的景観保護制度の誤った理解のもとで指導した問題について取り上げた。発表では、文化的景観の保護対象が有形の財ではなく「暮らし」「なりわい」であることを確認した上で、なぜ誤指導が生じたのか、文化的景観が文化財保護法と景観計画の二重適用に起因する解釈のズレがあったこと、それ以上に地元住民への適切な啓発・普及を疎かにしたまま「指導」や「罰則」で牽制し続けていたこと、等を明らかにしつつ、今後の国重要文化的景観地の持続的な保護と活用へ向けては、関係再生へ向け行政・文化財と地域社会・地元を橋渡しする対話と交流が必要であることを論じた。
いずれの発表においてもフロアから活発な議論が行われ、充実した研究発表会となった。発表会終了後、佐世保港やアーケード商店街周辺を巡るまちあるきが開催され、参加者は佐世保の魅力を体験するとともに、懇親会で親睦を深めた。
久留米大学
岩本洋一