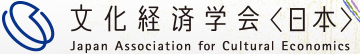九州部会活動報告(2025/3/2開催)
九州部会では、恒例行事となった第9回日本アートマネジメント学会九州部会との連携による研究発表会を2025年3月2日に熊本市現代美術館会議研修室で開催した。発表者は8名、参加者は21名とこれまででもっとも大きな規模となった。
第1部「芸術と社会」は志村聖子氏(相愛大学)が座長を務めた。
李紫涵氏(九州大学大学院)による「場づくりと人づくりの循環による文化の醸成––サザンクス筑後の「えんげきひろば」を例として––」では、子どもたちと演劇をつくる現場における場づくりと人づくりの循環についてフィールドワークを通じて論じた。フロアからはファシリテーターの役割、参加者である子どもたちの参加理由などについての質問がなされた。
岡田秀子氏(むすんでひらいて音楽事務所代表)・近藤浩平氏(作曲家)による「社会的ハンディを持つ演奏家・実践者の表現の場づくりマネジメント〜左手ピアニストの場合〜」では、左手のワンハンドピアニストである発表者自身による実践紹介とそれに基づいた考察が行われた。フロアからは実際の演奏の様子やワンハンドピアノをめぐる社会的な現状などについて質問がなされた。
第2部「市民と参加」は長津結一郎(九州大学)が座長を務めた。
GAO PEIYAO氏(九州大学大学院)による「参加者の視点で見る「リポーター」の実態:SMAART 2023の活動を対象」では、佐賀で実施された市民講座の一環で構築されたメディアのレポーターに着目し、鑑賞者の立場を多角的な分析した発表が行われた。講座の概要についてや調査者の立場、ファシリテーションの工夫などのについて質問がなされた。
藤原旅人氏(東京藝術大学)による「アート創造と市民醸成の創発を促すアートボランティア活動を振り返る〜10年の時を経て、市民は何を獲得しどんな役割を担おうとしているのか〜」では、さいたま市で行われてきた芸術祭におけるサポーターの10年間における役割の変遷を回顧する発表が行われ、サポーターのより詳しい実態やアーツカウンシルさいたまとの関係性などについて議論が行われた。
藤原惠洋氏(九州大学名誉教授)による「路傍の創造的生活達人アルティザンを招来する手づくり市民公開講座アルティザン・トーク、地域人材創発型中間支援プラットフォームの可能性とその意義〜大分県竹田市民公開講座アルティザン・トークを巡って」では、発表者が竹田市を拠点に継続的に実施している「路傍の達人」と呼ぶべき市民たちの語りを引き出す場を運営してきた経験と、そこからの考察が述べられた。質疑では企画を実現するにあたってのプロセスなどについての意見交換がなされた。
第3部「文化と価値」では岩本洋一氏(久留米大学)が座長を務めた。
中西美穂氏(立命館大学)による「日本占領下におけるフィリピンのミュージアムコレクションへのまなざし」では、ポストコロニアルな視点からミュージアムコレクションをどのように考えていくべきか、日本占領下におけるフィリピンの事例をもとに検討する発表が行われ、事例選定の理由や、ポストコロニアルな視点に関する議論が行われた。
志村聖子氏(相愛大学)による「伝統芸能におけるキュレーション概念を考える:伝統/革新/価値の再構築」では、伝統芸能に関する人材育成事業を事例として、とくに若年層に対してどのように伝統芸能の担い手としての価値を継承するかという課題について、実践的な視点からの議論が提起された。
中村美亜氏(九州大学)による「事業価値を可視化できる指標づくりの試み—アーツコミッション・ヨコハマでのアウトカム・ハーベスティングを用いた発展的評価」では、横浜市での事例や評価学に関する知見をもとにした実践に関する紹介と考察がなされ、フロアからは実践現場からの質問が相次いだ。
会は終始和やかな雰囲気で、終了後は有志での懇親会も熊本市内で実施し、さらに親睦を深め、こちらも非常に意義深い会となった。
九州大学大学院芸術工学研究院准教授
長津結一郎