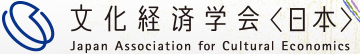2024秋の講演会報告

2024年11月17日(日)、「伝統工芸の未来に向けた新たな政策」をテーマに、2024年度秋の講演会が開催されました。本学会の新しい取り組みのひとつである「オンライン部会」のひとつとして、昨年度より活発にい活動されている「産業としての伝統工芸研究会」での研究成果を踏まえて企画されたもので、以下の5名のゲストをお迎えし(登壇順)、伝統工芸産業が抱える構造的問題やそのポテンシャルと今後の展望について、さまざまな観点からご議論いただきました。
- 山口徳彦 氏(経済産業省 文化創造産業課伝統的工芸品産業室)
- 秋山祐貴子 氏(輪島塗職人)
- 安嶋是晴 氏(会員・富山大学)
- 加茂勝康 氏〔タケフナイフビレッジ協同組合/加茂刃物製作所〕
- 中澤義晴 氏〔日本貿易振興機構(JETRO)デジタルマーケティング部〕
最初に、この研究会の世話役であり、今回の講演会でもコーディネーターを務めていただいた後藤和子会員(摂南大学)と高島知佐子会員(静岡文化芸術大学)から近年の日本の伝統工芸産業の概観が説明され、さまざまな困難はありつつも検討している状況が統計データから確認されることが示されました。
第1部として、5人の登壇者から、それぞれの視点に立った話題提供がありました。まず、山口氏からは、法律上の「伝統的工芸品」の定義と近年の指定状況など制度に関する話題や、伝統工芸品が抱える課題の説明のあと、伝統的工芸品の販売に向けた、さまざまな取り組みが紹介されました。議論の中で山口市が伝統敵工芸品を残さなければならないのは「供給側の都合ではない」と強調されている点が非常に印象的でした。
つぎに、秋山氏からは、2024年1月の能登半島地震と9月の奥能登豪雨の被害状況と復興に向けた状況とが示された上で、以前から課題となっていた担い手不足やサプライチェーンの維持が震災後より深刻になっていることが報告されました。一方で、復興の兆しも見られる中、伝統産業にとっては、今までの在り方も認めつつ、様々な分野と連携してチャレンジしてゆくことが必要であると強調されました。
そうしたチャレンジをいち早く実践された事例として、タケフナイフビレッジの加茂氏からは、1980年代にデザイナーの川崎和男氏とともに取り組んだ事業の事例や、共同工房および協同組合設立の経緯が紹介されました。武生では、ナイフビレッジに若い職人が集まるようになり、そこから独立して新しい工房を建てる事例も出始めているとのことで、日本の伝統産業の今後の在り方について、ひとつのモデルケースが示されたように見えました。
もうひとつの新しい取り組みとして、安嶋氏からは、産業観光との連携が提案され、富山県における伝統産業を取り入れた産業観光の興味深い事例が紹介されました。産業観光の難しさは、それが直接的に事業者の利益に繋がりにくいという点であるため、観光というコト消費をモノ消費につなげ、事例のひとつとして紹介された高岡の鋳造製品メーカーの「能作」のようにビジネス化することが重要であると指摘されました。
最後に登壇したJETROの中澤氏からは、中小・小規模事業者による海外への輸出を支援するTakumi next 2024や、JETROが招待する海外バイヤー専用のオンラインカタログJapan Streetなどの事例が紹介されました。そして、マーケティングの4つのP即ち、Price(価格)、Promotion(販売促進)、Place(流通)、Product(製品)のうち、海外側の状況で決まる前三者をいかに理解し、国内で決まるプロダクトを以下に大事にしていくことが重要であることが述べられました。
第2部のディスカッションでは、以上のプレゼンテーションを踏まえ、興味深い議論が展開され、コーディネーターから、職人が世界に積極的に繋がっていくことが重要であり、それを支援するための施策が必要であることがまとめとして述べられました。
今回の講演会は、京都橘大学を配信会場とし、会場での対面参加とオンラインでの参加との両方を可能とする新しい試みを行いましたが、対面での参加が約20名、オンラインでの参加が常時約30名(参加登録は70目)となり、大変盛況のうちに終えることができました。
京都橘大学 阪本 崇