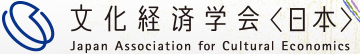文化経済学会<日本>会長就任にあたって
文化経済学会<日本>第17期会長
川井田 祥子
2024年7月から第17期会長を務めることになったのを機に自己紹介と、今後の学会活動で取り組みたいことを述べてみたい。
私が文化経済学という学問を知ったのは2003年で、当時は應典院という大阪市の寺院でディレクターを務め、現代アートの展覧会や演劇祭等の企画運営に携わっていた。應典院は寺が本来有していた機能、すなわち地域の教育や文化の振興に寄与する活動を展開すべく1997年に再建された浄土宗の塔頭寺院である。事業のための費用は、寺町倶楽部という会員組織からの会費収入と企業協賛によるところが大きく、支援者への説明のために「文化事業がもたらす効果について」等の根拠となる理論を探し求めていた。
また、2003年は大阪市立大学に大学院創造都市研究科が開設された年であり、市大に着任された佐々木雅幸先生の講演や国際シンポジウムを聴講して最新の知見を得る機会に恵まれた。文化経済学会の存在も知り、もっと情報を入手したいと考えて入会したのが2004年である。実務経験しかない者の入会を認めるという、学会の門戸が広く開かれていることをとてもありがたく感じた。
その後、「もっと学びたい」という思いが強まり、2007年に大阪市大大学院へ入学した。創造都市論登場の背景には社会的排除の克服という政策課題があったことを知り、自身の研究テーマを「障害者の表現活動による社会的包摂」とし、文化と福祉を架橋すべく研究者の道を歩み始めることとなった。
近年ではwell-beingという概念が重視され、たとえばWHOが2021年に発表した “Towards developing WHO’s agenda on well-being” には、経済主導の社会からwell-beingを中心とした社会への転換が必要であると記されている。障害者のみならず、誰にとってもwell-beingを実感できる社会が求められていると言えよう。当学会の存在意義が問われているとも考えられ、ますます身の引き締まる思いである。
*****
片山泰輔先生が会長を務められた第16期では、研究大会や秋の講演会といった諸事業の充実に加え、学会運営に重要な役割を果たしている各委員会の活動について、会則上の位置づけを明確化する等、諸規定の見直しにも取り組んだ。委員会活動を通じて会員の学会運営への参画を促すとともに、学会内外にその貢献を示せるようにすることが目的である。たとえば学会ホームページの「役員・委員等」欄の下部には、委員等分担表を掲載しており、役員のみならず会員も各委員として活動していることがわかっていただけるであろう。今期も引き続き各委員会の活動を顕在化させながら、より多くの会員が学会運営に参画できるよう努めていきたい。
会員数を増やすことも喫緊の課題である。その方策の一つとして、学会活動の情報発信について議論を重ねた結果、ニューズレターをPDF形式で発行することを今号限りとし、以降はホームページ(HP)に情報を掲載していくよう準備を進めている。めざすべきHPの機能は、①学会の広報媒体として、②会員のプラットフォームとして、の2つである。①については、文化経済学が多様な学術的アプローチを包含する学際的領域であり、研究と実社会との結びつきを重視していることを伝える、②については、会員間での研究や実践の交流を促すとともに、海外の動向等も含めた情報提供を行っていく、ということをめざしている。なるべく多くの会員に原稿執筆を依頼することを想定しているので、ぜひ協力をお願いしたい。
学会運営に参画する機会を増やし、多様な専門領域をもった会員一人ひとりが、当学会の価値を実感できるように努めていく所存である。