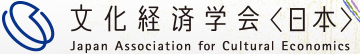文化芸術のEBPMの潮流について
名城大学 経済学部 教授
勝浦 正樹
■ EBPMと文化芸術
近年、EBPM(Evidence Based Policy Making; 証拠に基づく政策立案)という言葉をよく耳にする。政策目的を明確化した上で関連する様々な情報や統計等のデータを活用し、政府による政策の企画をエビデンス(証拠、合理的根拠)に基づいて行うという意味である1)。単に過去の経験やその場限りの直感に基づくのではなく(エピソード・ベース)、データや適切な分析結果をもとに客観的・論理的に政策を立案するというメッセージが込められていると筆者は考えている。もちろん、エビデンス・ベースで立案したからといってうまくいくとは限らないが、政策の企画や評価からできる限り主観を排除するというスタンスは重要である。では、文化政策については、どうだろうか。
そもそも文化とは抽象的な要素が多く、伝統が重んじられるものであって、客観的な数値で表すことは困難であると主張されることも少なくなかったように思われる。しかしだからといって、文化政策を検討する際にエピソードに頼るだけで、客観的なデータや実証分析を放棄することは適切ではない。たとえば、歌舞伎や文楽の面白さや価値を客観的データ等で説明することは難しいかもしれないが、観客数、演目数、俳優・演者数等々、利用可能なデータも少なくないはずである。
■ 指標検討のための有識者会議
2013年3月に決定された「文化芸術推進基本計画(第2期)」(以下、第2期計画)では、「EBPMの理念に則り、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用して、取り組むべき施策を総合的かつ多角的に判断・評価し、合理的な根拠(エビデンス)に基づき、効率的かつ効果的に文化芸術政策を推進していく必要がある」と明示されており、「中間評価の際の指標については、…(中略)…、その精選を文化審議会文化政策部会を中心に行うこととする」としている2)。そして、同計画の進捗状況を把握するための指標について専門的な検討を行うため、「文化芸術推進基本計画(第2期)指標検討のための有識者会議」(座長:河島伸子同志社大学教授、以下、有識者会議)が2024年1月に組織され、具体的な指標やその数値目標が議論された3)。有識者会議の構成員には、座長・筆者をはじめ文化経済学会<日本>の会員も多く含まれている。
有識者会議では、第2期計画で掲げられた7つの重点取組(①ポストコロナの創造的な文化芸術活動の推進、…、⑦デジタル技術を活用した文化芸術活動の推進)ごとに設定された複数の目標それぞれについて、目標の進捗状況を把握するためのいくつかの「指標」が精選され、それらの指標ごとに目標値を定めるという作業が行われた。たとえば、重点取組①の第1の目標である「コロナ禍からの復興と文化芸術水準の向上等」では、文化庁による人材育成事業の研修に参加した芸術家等の人数を指標として、その目標値を何名以上と定めるとか、「文化に関する世論調査」における舞台芸術などの鑑賞割合(参加率)を指標として、2027年にはその割合を何%以上とするといった具合である。これは一例で、非常に多くの指標とその目標値が設定されており、詳細は注3) のURLから辿れる有識者会議の配布資料を参照されたい。
ここで目標値については、いくつかの注意が必要である。まず、指標はその目標値を達成することよりも、計画を評価・検証するためのよりどころと位置づけられている。また、すべての目標が定量的に評価できるとは限らず、定性的な評価も含まれる。さらに目標値については、現状の値を踏まえた上で、有識者や関連団体からのコメントも反映した上で、その設定の根拠をできるだけ明示するとともに、目標を達成するための手段からどのように目標が導かれるかというロジックが理論的に展開されている。政策のアウトプットとインプットの関係が実証分析の結果に基づいているとは限らないなどの課題はあるけれども、このような方向性で検討が行われ、第2期計画の評価にEBPMの考え方が反映されていることには一定の評価が与えられるべきであり、今後の評価や重点取組の達成状況を注視していく必要がある。
■ EBPMを実現させる要素
わが国においてEBPM という概念が浸透した経緯に関しては、いくつかの研究がある。たとえば田中 (2020) は、2016年10 月に発足した「EBPM のニーズに対応する経済統計の諸課題に関する研究会」や同年12 月に経済財政諮問会議で示された「統計改革の基本方針」などが、EBPMの推進のきっかけとなったという見方をしている4)。つまり、EBPM と統計改革がセットになっており、統計改革を行うためにEBPM という概念が利用されたというと極端かもしれないが、EBPM を定着させるためには統計改革が必要であったと考えられる。もちろん、統計を充実させただけEBPMが実現するわけではない。統計データによって現状や目標を記述するだけでなく、データを用いて因果推論をはじめとする統計的手法に基づいた政策分析が必須となる。
このように考えれば、文化政策におけるEBPMの実現には、文化統計の充実とともに統計データを用いた政策立案・評価のための分析の蓄積が必要となる。しかし、文化に関する統計データを得るために新たな統計調査を実施することは、予算や人的な制約などから非常に困難である(もちろん、EBPMを担う能力のある人材育成も重要な課題である)。しかし、文化庁が実施する「文化に関する世論調査」などの統計調査をより充実させていくことは可能であるし、文化庁以外の省庁や民間に分散している既存の公的・民間統計の中から、文化に関連する統計データを一定の枠組みのもとで収集し、公表していくことは、文化統計の充実に他ならない。たとえば、芸術家の数であれば、総務省「国勢調査」などが利用できるし、文化産業については、総務省・経済産業省「経済センサス」などが有用であろう。したがって、様々な統計調査から文化芸術に関する必要な情報を抽出し、文化統計として体系的に整備していくことが現実的であり、そのためには、該当する調査の個票情報(ミクロデータ)を用いて、文化芸術に関する独自の集計を行うなど様々なアプローチが可能である。
文化に関するデータについては、西欧諸国に比して、わが国の統計はあまり体系化されていないという指摘もある5)。文化庁のウェブサイトにおける統計のリンク先をみても、残念ながら諸外国のように文化の状況が概観できるようなコンテンツにはなっていない。一方、文化庁が作成しているデータ集として「文化芸術統計関連データ集」6) があり、かなり有用な情報が掲載されているが、あくまでも文化庁の審議会や有識者会議などにおける資料として不定期に作成されているという位置づけのようである。同データ集をもう一歩進めて、体系的な文化芸術に関するデータ集を作成していくことも、EBPMを推進するためには必要な手段の一つであろう。
有識者会議等での検討や研究者による様々な研究が、文化統計の充実につながり、今後のエビデンス・ベースの文化政策を実現するために役立つことを期待したい。
注
- https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html
- https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/hoshin/
- https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/yushikisyakaigi/index.html
- 田中啓(2020)「「霞ヶ関改革運動」としての政府のEBPM 推進 - その意義・課題と今後の展望 -」『季刊行政管理研究』No.191,21-39 ページ。
- 文化庁・名城大学 (2023)『令和4年度文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業「文化統計の体系化に関する調査・研究」報告書』を参照のこと。同報告書では、欧米諸国の文化統計の体系化についての比較がなされている。
- https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/yushikisyakaigi/02/pdf/94013101_05.pdf